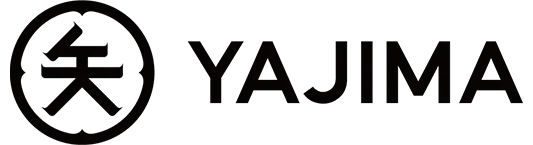災害リスク、地盤の弱さなど土地選びで見落としがちな特徴は、ご家族の安全と資産価値を大きく左右します。
理想の家づくりができても、土地が悪ければ台無しになりかねません。
災害リスクや地盤の問題、周辺環境など、見落としがちなポイントが多数あります。
本記事では、住んではいけない土地の特徴や見分け方、専門家への相談方法などわかりやすく解説します。
ご家族で幸せに暮らせる安全な住まいを手に入れるために、土地選びの知識を身につけたい方は、ぜひ最後までごらんください。
| このコラムのポイント |
|---|
| ・災害リスクが高い土地や地盤に問題がある場所は、住んではいけない土地の代表的な特徴です。 ・土地選びでは形状や周辺環境、接道状況などを事前に確認することが大切です。 ・後悔しない土地選びには、ハザードマップの確認や現地訪問、専門家への相談が効果的です。 |
Contents
住んではいけない土地の特徴

マイホームを購入する際、土地の立地や価格だけで判断すると、将来大きな後悔につながることがあります。
ここでは、避けるべき土地の特徴をご紹介します。
災害リスクが高い
ご家族の安全を第一に考えるなら、災害リスクの高い土地は避けるべきです。
国や自治体が公開しているハザードマップでは、自然災害による被害が想定される区域が指定されています。
これらのエリアは、過去の災害データや地形から危険性が認められているため、購入を検討する際は慎重な判断が必要です。
- ・洪水・津波浸水想定区域内の土地
- ・土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の土地
近年は気候変動の影響で、過去に水害がなかった地域でも大規模な洪水が発生するケースが増えています。
国土交通省によるハザードマップで、購入予定地の災害リスクを必ず確認しましょう。
地盤・土壌の安全性に問題がある
以下のように地盤や土壌に問題がある土地は、後々トラブルが発生するリスクが高いため要注意です。
- ・液状化リスクが高い
- ・地盤が軟弱で不同沈下の恐れがある
- ・過去に地盤沈下が起きている
これらに該当するのは埋立地や盛土の土地です。
埋立地や盛土の土地は地震時に液状化現象が起こりやすく、建物に被害が生じる可能性があります。
軟弱地盤は不同沈下を起こし、建物にひび割れなどの損傷を引き起こすリスクがあります。
危険な道路がある
交通事故が多発するエリアや見通しの悪い道路沿いは、特に小さなお子さんがいるご家庭では避けたい場所です。
急カーブや抜け道として使われる道路沿いの土地は、車の走行速度が速く、危険が増します。
通学路となる道路の安全性が確保されているか、あわせて確認しましょう。
住む前に確認が必要な土地の特徴

住んではいけない土地ほど明確なリスクはなくても、住む前に必ず確認すべき土地の特徴があります。
- ・地形・形状に問題がある
- ・擁壁がある
- ・アクセス・利便性が悪い
- ・周辺環境に問題がある
- ・接道義務を満たしていない
- ・市街化調整区域にある
- ・境界があいまい
これらは見落とすと後悔につながる可能性があるため、事前に把握しておきましょう。
地形・形状に問題がある
土地の形状によっては建物の建築可能範囲が限られたり、生活の利便性が悪くなったりすることがあります。
以下のような形状の土地は、将来的な不便さや資産価値の低下につながるため、購入前によく検討する必要があります。
- ・旗竿地(はたざおち)
- ・細長い土地
- ・不整形な土地
- ・高低差が激しい土地
旗竿地とは、道路に接する間口が狭く、細長い通路(竿部分)を通って奥に入ったところに、まとまった敷地(旗部分)が広がっている土地のことです。
旗竿地は日当たりやプライバシーの問題だけでなく、将来売却する際にも価格が下がりやすい点がデメリットです。
高低差のある土地では、造成工事や擁壁の設置に追加費用がかかる上、日常生活での移動が不便になることもあります。
小さなお子さまやご高齢の方がいるご家庭では、将来的な負担を考慮して平坦な土地を選ぶことをおすすめします。
擁壁がある

傾斜地に設けられる擁壁(ようへき)には土地が崩れないように支える役割があります。
老朽化した擁壁の崩壊は、大きな災害につながりかねません。
擁壁のある土地を検討する際には、以下のポイントを必ずチェックしましょう。
- ・擁壁の種類と状態(コンクリート製、石積み、土留めなど)
- ・ひび割れや傾きなどの劣化症状
- ・擁壁の高さと角度
- ・水抜き穴の有無
古い擁壁は地震の際に崩壊するリスクが高くなります。
高さ2m、幅10mの擁壁をつくる場合、100~200万円前後の費用がかかると言われているため、購入前に擁壁の安全性と今後必要となるメンテナンス費用について確認しておく必要があります。
擁壁の耐用年数やメンテナンス方法について、こちらで解説しているのでぜひ参考にしてください。
〈関連コラム〉擁壁の耐用年数は何年?古い擁壁の崩壊を防ぐためのメンテナンス方法とは
アクセス・利便性が悪い
現在は車での移動が中心でも、将来的なライフスタイルの変化を考えると、公共交通機関や生活利便施設へのアクセスは確認しておきたいポイントです。
以下のような特徴がある土地は、長期的な視点で考えると不便さが際立ってくる可能性があります。
- ・最寄り駅から遠い
- ・バス便が少ない
- ・公共交通機関がない
- ・スーパーやコンビニなどの生活施設が遠い
- ・坂道が多いエリア
若いうちは気にならなくても、将来車の運転が難しくなれば、日常生活に支障をきたす恐れがあります。
不動産の価値は駅からの距離に大きく左右されるため、将来の売却を考えると、駅から遠い土地は資産価値が上がりにくいという点も念頭に置いておきましょう。
周辺環境に問題がある
住宅を建てた後は簡単に移動できないため、周辺環境の良し悪しは生活の質に直結します。
騒音や悪臭といった問題は、一度住み始めると解決が難しいため、購入前には以下の環境要因を確認しておきましょう。
- ・騒音源(幹線道路、鉄道、工場、空港など)が近い
- ・悪臭の発生源(工場、畜産施設など)が近い
- ・日当たりが悪い
- ・高圧線や鉄塔が近い
特に騒音は時間帯によって変わるため、一度の訪問では気づかないこともあります。
平日・休日の昼夜それぞれ異なる時間帯に現地を訪れると、より周辺環境を理解できます。
境界があいまい

土地の境界が明確でない場合、将来的に隣地との間でトラブルが発生するリスクがあります。
境界問題は解決に時間とコストがかかるだけでなく、精神的な負担も大きいため、購入前には以下のような点を必ず確認しましょう。
- ・境界標(境界杭)が設置されていない
- ・境界確定測量が実施されていない
- ・公図と現況が一致していない
境界があいまいな土地を購入すると、後々隣地との間で「ここからここまでが自分の土地」という認識の違いからトラブルになることがあります。
接道義務を満たしていない
建築基準法では、建物を建てるための敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという「接道義務」が定められています。
この条件を満たさない土地では、原則として建物を建てられません。
注意すべきなのは、現在建物が建っていても、将来建て替える際に接道義務を満たせなくなる可能性のある土地です。
このような制約を抱える土地は、資産価値が低下しやすいため、購入は慎重に検討しましょう。
市街化調整区域にある
都市計画法に基づく「市街化調整区域」は、市街化を抑制すべき区域として農地や緑地の保全が優先される地域です。
自然豊かな環境に惹かれて購入を検討する方もいますが、以下のような制限があります。
- ・原則として新たな宅地開発や建物の建築が制限される
- ・既存の建物がある場合でも、建て替えに制限がある
市街化調整区域内の土地は価格が安いことが多く、一見すると魅力的に見えます。
しかし、現在は許可を得て建てられている建物でも、将来的に同じ条件で建て替えができなくなる可能性もあります。
住んではいけない土地の見分け方・調査方法

土地購入でのミスを避けるには、調査と情報収集が欠かせません。
ここでは具体的な見分け方と調査方法について解説します。
土地について情報収集する
土地の履歴や特性を知るための情報収集は、インターネットや公的機関で容易にできます。
以下のような方法で、土地に関する情報を集めましょう。
- ・ハザードマップの確認(洪水、土砂災害、地震被害想定など)
- ・法務局での登記情報の確認
- ・自治体で用途地域や建築規制の確認
法務局で取得できる登記簿謄本からは所有権の歴史や抵当権の有無などを、公図からは土地の形状や周辺状況を確認できます。
法務局で直接確認する他に、インターネットや郵送で取得する方法もあります。
参照:登記情報提供サービス
現地を確認する
机上での情報収集だけでなく、現地を何度か訪れることが土地選びの成功につながります。
雨の日に現地を確認すると、水たまりができやすい場所、雨音が気になる場所など、晴れた日にはわからない問題点が見えてくることがあります。
また、朝の通勤時間帯や夕方の下校時間など、人や車の動きが活発な時間帯に訪れることで、交通量や騒音レベルを把握することも大切です。
専門家へ相談する
素人目ではわからない土地の問題点を見抜くためには、専門家の知識を借りるのがおすすめです。
- ・建築士による建築可能性診断や境界確認
- ・地盤調査会社による地盤調査
地盤調査費用は数万円〜数十万円程度かかりますが、将来追加工事が必要になるリスクを考えれば、十分に価値のある投資といえます。
建築会社によっては、建てる前提であれば、調査費用を建築費用に充当してくれる会社もあるため、検討している会社へ確認しましょう。
土地選びで後悔しない方法

住んではいけない土地を避け、理想の住まいを実現するためのポイントを紹介します。
予算とのバランスを冷静に考える
理想の土地を求めるあまり、予算オーバーになるケースが少なくありません。
土地購入にかける予算は、住宅建築費や諸経費、将来的なメンテナンス費用なども考慮して決めることが大切です。
住んではいけない土地の特徴を避けようとすると、予算が膨らみがちです。
しかし、無理な予算で購入すると、住宅ローンの返済負担が重くなり、ご家族の生活が苦しくなる恐れがあります。
長期的な家計のバランスを考え、無理のない範囲で最良の選択をしましょう。
複数の候補を比較する
一つの土地だけを見て、その土地が良いか判断するのは難しいため、複数の候補を比較検討しましょう。
条件の良い土地はすぐに売れてしまうため、焦って決断してしまいがちですが、複数の候補を見ることで各土地の特徴や問題点を把握できます。
エリアの異なる土地や、駅からの距離や土地の広さなど条件の異なる土地を比較することで、ご家庭にとって本当に優先すべき条件が明確になります。
土地選びに関するQ&A

矢島建設工業がよくいただく、土地選びに関するよくある質問とその回答をまとめました。
Q.洪水や土砂災害のリスクが高い土地の見分け方は?
洪水や土砂災害のリスクが高い土地は、ハザードマップで確認できます。
国土交通省や各自治体のウェブサイトで公開されているハザードマップを必ずチェックしましょう。
過去の災害履歴だけでなく、シミュレーションに基づく将来的なリスク予測も確認できます。
Q.地盤が弱い土地を見分ける方法はありますか?
地盤の強さは目視だけでは判断が難しいため、専門の地盤調査会社による調査が有効です。
ただし、以下のような特徴がある土地は、地盤が弱い可能性が高いと考えられます。
- ・周辺の建物に不同沈下の跡(傾きやひび割れ)がある
- ・かつて沼地や池、田んぼだった土地
- ・埋立地や盛土地域
確実に判断するには、地盤調査の実施がおすすめです。
Q.土地に高低差がある場合の注意点は?
土地に高低差がある場合、造成費用が追加でかかることを見込んでおきましょう。
平坦な土地に比べて、擁壁の設置や盛土・切土の工事が必要になるため、建築コストが増加します。
擁壁の状態が良くなかったり、排水計画が不十分だったりすると、豪雨時に土砂崩れや水害のリスクが高まります。
擁壁は専門家に点検してもらい、水抜き穴の状態や雨水の流れる方向も確認すると安心です。
擁壁について、こちらの記事で詳しく解説しています。
〈関連コラム〉擁壁のある土地はやめた方がいい?後悔を防ぐ購入時のチェックポイント
まとめ
土地選びでは複数の候補地を比較検討し、価格だけで判断せず、なぜその土地が相場より安いのかを理解することも大切です。
また、購入後の住宅建設費用や将来的な維持管理コストも含めた総コストを計算し、無理のない予算計画を立てましょう。
矢島建設工業では、土地選びのプロが候補地の現地調査を行い、擁壁の状態や地盤の安全性を専門的な視点からアドバイスいたします。
これから家族が長く安心して暮らせる土地かどうか、中立的な立場でご判断をサポートします。
ぜひお気軽にご相談ください。